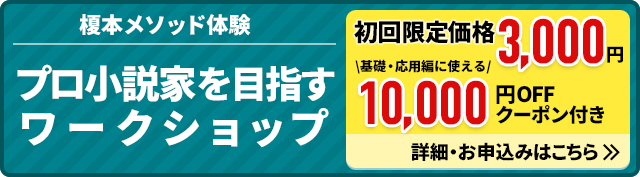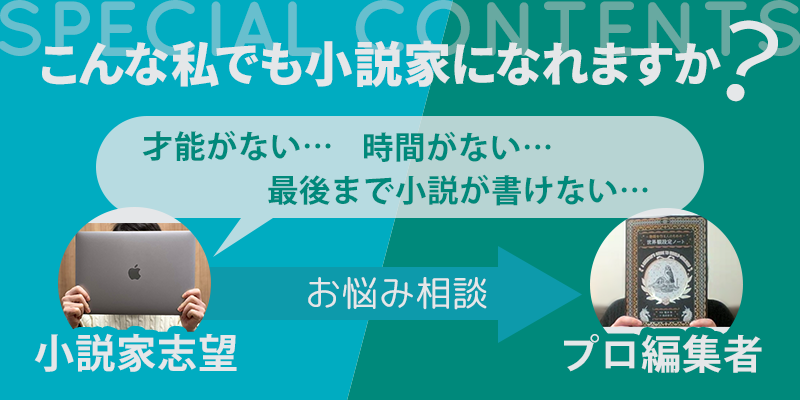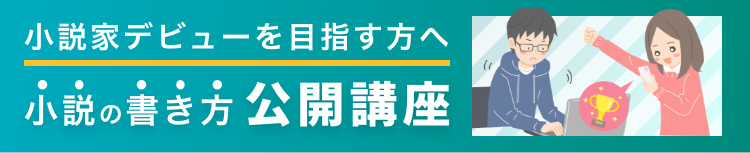

小説の書き出しは「面白い」がマスト! 冒頭で心をつかむ書き方・テクニックとは
小説の書き出しはとても重要な部分です。物語のはじまりをどのように書くかで、そのまま続きを読み進めてもらえるかどうかが決まるといってもいいでしょう。
その大事な冒頭部分で長々とキャラクターや世界観の説明がはじまったら、読者は退屈してしまいますよね。
今回はそうならないために「冒頭のエピソードで物語に引き付けるパターン」についてご紹介します。読者の関心をグッと掴んで、物語の世界に引き込むきっかけを作っていきましょう。
目次
小説の書き出しでやってはいけないこと!

読者が続きを読んでくれるかどうかの重要な分岐点「小説の冒頭部分」は、何から書きはじめればいいのだろうと悩む方も多いパートです。
ここでは小説の冒頭で読者が離れてしまいがちな悪い例をご紹介します。
説明語りはNG
小説を書きなれていない方がやってしまいがちなのは「律儀に説明から書きはじめてしまう」ケースです。
「冒頭でしっかりとキャラクターや世界設定の説明をしなくては!」とつい意気込んでしまう気持ちはよくわかります。それでも設定の説明やキャラクターについてよく知ってもらうためだけに作られたシーンばかりでは「物語としては退屈」な構成になりやすいものです。
読者が求めているのは、物語であって設定資料ではありません。
冒頭から物語の説明がはじまっても、読者にとっては退屈なだけ。もちろん設定を説明することは大切ですが、物語より先に設定が来てしまっては本末転倒なのです。
たとえばミステリー作品において、殺人が起きる前に「その舞台となる館の詳細」や「そこにいる家族の関係」の説明がはじまったとしたらどう感じるでしょうか。
一番インパクトがあって読者が楽しみにしているシーンは、そこではありません。肝心なのは「人が殺されるシーン」なのです。
そのことから、冒頭でなるべく早く殺人シーンを書いて、詳しい説明は後回しにするようなストーリー構成が時には必要になります。
見どころの出し惜しみはNG
また主人公の性格や能力、キャラクター同士の関係性など、作品の見どころになってくる部分を、冒頭でみせるというやり方もあります。
それがわかるエピソードを最初に持ってくることで「こんな話がはじまるんだな」と読者に知らせる、親切な設計になるのです。
面白くなる部分は後に取っておいて……と出し惜しんでいると、話が盛り上がる前に読者が離脱してしまうことも。印象的なシーンは冒頭にもってきて、期待値を上げましょう。
書き出しは勢いよく行こう|「起」起承転結型ストーリー

物語の基本である「起承転結」はストーリーの理想的な流れとして知られています。しかしこの方法はあくまで基本です。これにどのようなアレンジを加えるかが小説家として腕の見せどころでしょう。
その発展型が「起、起承転結型」という物語のパターンです。
起・起承転結って何
物語の導入部分にあたる「起」が1つ多いのはどういうことでしょうか。この追加された「起」とは、主に物語の本筋とは関係のない事件を題材としたエピソードのことです。
ここでは物語本編(起承転結)の前に起きた小さな事件を描きます。
メリット1|設定紹介がスムーズ
起・起承転結型ストーリーのメリットは、自然な流れで設定を提示できること。冒頭で語られる事件によってキャラクターや世界設定などが自然な形で明らかになるというわけです。
特にこの場面で描きたいのは「主人公たちが活躍するシーン」。刑事ものなら犯人逮捕、探偵ものなら謎を解く場面が「起、起承転結」における最初の「起」にあたります。
- 彼らがどのような状況に置かれているのか
- この作品自体がどのような世界を舞台にしているのか
このあたりをしっかり取り入れながら、キャラクターが生きるエピソードをつくりましょう。衝撃的な展開で読者を引き付けると同時に、さりげなくキャラクターや世界の設定を提示できる一挙両得のスタイルです。
メリット2|伏線として活かせる
また、冒頭の事件は本編に関係のないものと思わせて、実はなんらかの形で大きなつながりがあった! というのも定番の伏線です。
- 冒頭の事件こそがすべての引き金だった
- 最初の事件で失敗した技術に挑戦して事件を解決する
このように、プラスアルファの価値をつけていくことで物語はもっと面白くなります。
さらに「起」の部分から過去の回想として本編がはじまるというパターンもよくあります。最初の「起」を制して、読者の興味を引きつけたまま本編へ入っていきましょう。
メリット3|本文への導入がスムーズになる
1つの小さな物語をダイジェストで描くことで、本編へとスムーズに入っていける効果が生まれます。
冒頭のショートストーリーが、本編で描かれる大きな展開へとつながっていく、これも余計な説明で物語のテンポを悪くしないために有効な方法です。
「起」起承転結型ストーリーのデメリット
冒頭に印象的なシーンを持ってくるデメリットは「説明不足になりがち」な側面があることです。
テンポを崩さないように意識すると、当然細かい説明ができません。しかし、物語を前提条件から順番に説明する書き方は前置きが長くなり、読者を退屈させてしまいます。
エンターテインメント小説を書くときは、あえて少し説明不足になったとしても、インパクトのあるシーンを最初に出すのがオススメです。
これはどういうこと? という引っ掛かりがあると先が気になって、続きが読みたくなるという効果も期待できます。
熱いシーンで惹きつけるテクニック|ホットスタート

「起、起承転結型」など、物語のパターンの1つにホット・スタートという手法があります。文字通り「熱い」展開から物語を書きはじめていくのが特徴です。
- いきなり日常空間が事件に巻き込まれる
- 学校がテロの現場になる
- 主人公が襲撃される
- 何者かに殺害されてなぜか復活する
こういった衝撃的で勢いのあるシーンから物語をスタートさせるのです。
ホットスタートの目的1|衝撃的なシーンで読者を飽きさせない
崩壊する日常、主人公の死、絶体絶命の危機などといった厳しい状況を最初から提示することで緊迫感や緊張感を生み出します。
ホットスタートの目的は、「これからどうなるんだ?」という展開を、あえて冒頭に置くことで物語としての勢いとおもしろさを引き出すこと。設定を語るのは後回しでいいのです。
ホットスタートの目的2|設定の解説が「自然に」できる
インパクトのためだけでなく、ホットスタートには主人公たちの能力や個性、その世界の設定を強くアピールする効果もあります。
すなわち、設定の説明が自然にはじめられるという利点があるのです。
冒頭に強烈なシーンをおくと、インパクトが強い一方で情報は足りません。すると読者は「このお話、おもしろそうだな」と期待しつつ「でも、あれってどういうことなんだろう?」と前のめりに物語と向き合うことに。
そうやって読者が自然に詳細を知りたくなったところで、満を持して説明をはじめます。この需要と供給がうまくいくと「あぁ、そういうことだったんだ!」と読者に満足してもらえるというわけです。
これからの展開を期待してもらうために、衝撃的かつ勢いのあるシーンで読者の心をつかみましょう。
冒頭のつかみはハリウッド映画から学べ|冒頭にミニエピソードを

激しいアクションシーンや衝撃的な事件が冒頭にあったり、小さなエピソードが挿入されているパターンはハリウッドのアクション映画でも多く使われる手法です。
『インディージョーンズ』の冒頭
インパクトのある冒頭で代表的な作品が『インディージョーンズ』シリーズの1作目である『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』です。
この映画は考古学者インディアナ・ジョーンズが、洞窟の中で探し求めていた黄金像を発見するところからスタートします。神殿からその秘宝を盗み出そうとするとトラップが作動。閉じてくる壁を間一髪ですり抜け、穴に落ちそうになり、転がってくる巨大な丸い岩から逃げ……
まさに飛んで走って滑り込んでと、ハラハラドキドキの熱い展開です。そして命からがら洞窟から脱出したものの、その先で武器を持った先住民族に包囲されてしまいます。
そんな息をもつかせぬシーンの連続の後、物語の主題にまつわるアーク(聖櫃)に関わっていくのです。
『007』シリーズの冒頭
人気スパイ映画「007」シリーズでも、まずジェームズ・ボンドが1つの任務を達成する姿が描かれます。その後にさらなる任務を命じられるというパターンで、本筋に入っていくのがお約束です。
冒頭のミニエピソードで「主人公たちの活躍」をみせる
このように冒頭で観客を釘付けにするフックが組み込まれていると、その映画への期待値があがり、物語の世界へ没入しやすくなりますよね。
冒険家なら迷宮での活躍。探偵なら事件の謎を解く様子。刑事なら犯人逮捕。ヒーローならヴィラン(敵役)との戦い。
冒頭に主人公たちが活躍するミニエピソードを入れることで、キャラクターの能力や個性を紹介する手法は、ハリウッド映画でもよくみられるストーリー構成です。
もちろん小説を書くときに、何でもかんでもこのような手法を使えばいいというものではありません。
しかし、特殊な世界設定を採用していて、事細かな説明を必要とする場合などで上手に取り入れるとよりおもしろい作品になることでしょう。
エンタメ小説は「最初からクライマックス!」を目指そう

クライマックスとは、物語の中でもっとも盛り上がる、緊張感や興奮が高まるシーンを指します。
もちろん本編でのクライマックスは最重要ですが、冒頭のエピソードもこれぐらいの勢いで書けるといいでしょう。
ここでは読者の気持ちを高めるためのテクニックをご紹介します。
テクニック1・魅力的なセリフ
読者の記憶に残るシーンを作るためには、「印象的なセリフ」が効果的です。キャラクターに印象的なセリフを言わせて、インパクトのあるシーンを作りましょう。
この場合のセリフは、長々としたものでは効果半減です。一言、一文で、覚えやすいものがオススメ。
そのセリフを言ったキャラクターがどういう人物なのかを一瞬でイメージさせる効果もあるため、上手に使いこなしましょう。
※印象的なセリフの書き方について詳しくはこちらの記事をご覧ください
セリフの書き方|台詞回し・掛け合い・会話文のコツと使い方のルール
テクニック2・文章にテンポを出す
建物の崩壊など何らかのタイムリミットが迫っているようなシチュエーションは、緊張感があり、盛り上がります。これらを冒頭に持ってくる場合は、テンポの良さを意識しましょう。
文章のテンポを良くするためによく使われるのは以下の方法です。
テクニック3・地の文を短く区切る
具体的には、地の文を短く区切ることで臨場感が出ます。意識して書きましょう。
テクニック4・オノマトペを使う
オノマトペとは擬声語(擬音語)や擬態語のこと。「カキーン!」「ガガガッ」「ザワザワ」などの効果音の描写です。
小説の文章にオノマトペを使うことで、イメージしやすいため読者の記憶に残りやすい、短い文章で表現できるのでテンポが落ちないという利点があります。
ただし使い過ぎると幼稚な文章になってしまうのもオノマトペの特徴です。使いどころに注意して活用しましょう。
※効果的なオノマトペの使い方について詳しくはこちらの記事をご覧ください
オノマトペの使い方|擬音語・擬態語を使うと文章はどうなる?
小説の書き出しで「ベタ(定番)」を恐れない!
物語の冒頭にインパクトを持ってくるのはよくあるパターンですが、「お決まりのパターン」は先人が積み上げてきた「こうすればおもしろくなる」という技術の塊なのです。
一見よくみる展開でも、工夫次第でオリジナリティは出てきます。それに見たこともない「独創的なもの」よりも、ベタなパターンにアレンジを効かせた「安心感のある」作品を好む読者は多いものです。
「待ってました!」という展開を上手に取り入れ、オリジナリティのある冒頭シーンをつくりましょう。
物語のおもしろさは出だしで決まる!
読者の関心を引く「おもしろいエピソード」を冒頭にもってくることで、主人公や主要キャラクターの個性や世界設定を紹介できます。
そのうえ「これからどうなるんだろう」という読み手の興味を掻き立てることもできるのです。
冒頭にインパクトの強いエピソードがあると、次に続く説明パートへの関心にもつながります。さらに伏線も張れれば、物語のクオリティは格段にアップします。
「起、起承転結型」や「ホットスタート」を上手に使って読者を物語の世界へぐいぐいと引き込みましょう。
※基本的なストーリーの作り方については以下のコラムを参照してください。
・起承転結と序破急のポイントと応用|知っておきたいストーリーの作り方
この記事は小説家デビューを目指す方を対象に作られた小説の書き方公開講座です。
幅広いテーマで書かれた数多くの記事を無料でお読みいただけます。
榎本メソッド小説講座 -Online- のご案内
お読みいただいているページは、現場で活躍する小説家・編集者・専門学校講師が講師を務める、小説家デビューを目的としたオンライン講座「榎本メソッド小説講座 -Online-」の公開講座です。小説家デビューに向けてより深く体系的に学習したい、現役プロの講評を受けてみたいといった方は、是非本編の受講をご検討ください。
監修|榎本 秋
1977年東京生。2000年より、IT・歴史系ライターの仕事を始め、専門学校講師・書店でのWEBサイト企画や販売促進に関わったあと、ライトノベル再発見ブームにライター、著者として関わる。2007年に榎本事務所の設立に関与し、以降はプロデューサー、スーパーバイザーとして関わる。専門学校などでの講義経験を元に制作した小説創作指南本は日本一の刊行数を誇っており、自身も本名名義で時代小説を執筆している。
同じカテゴリでよく読まれている公開講座
-
太宰・芥川編|小説の語彙力・表現力・発想力の勉強方法
語彙力や表現力、発想力を鍛えるためには小説をただひたすら書き続けるよりも、「読む」ことが近道です。なかでもオススメなのが明治から昭和にかけて発表された「文学」作品と呼ばれるジャンルを読むこと。 今回は、不朽の名作を生み出 […]
-
掌編小説の書き方
小説家志望者のなかには、まだ長編を書いたことがないという方も多いのではないでしょうか。長編を完成させる力を付けるためには、まず掌編小説をいくつか書き上げる練習法がオススメです。今回は掌編小説を書くときに気をつけるポイント […]
-
小説の展開を面白くするためにプロがやっていること
小説の展開を面白くするには、「オリジナリティー = 斬新なストーリー展開」が必要だと思っている方は多いようです。 読者をあっと言わせるために「誰も見たことのない物語を作りたい」という目標は素晴らしいですが、誰にでもできる […]
公開講座 - 目次
カテゴリから探す
ジャンルから探す
人気の公開講座