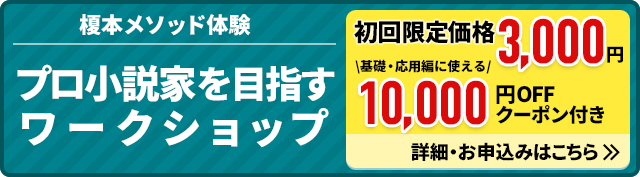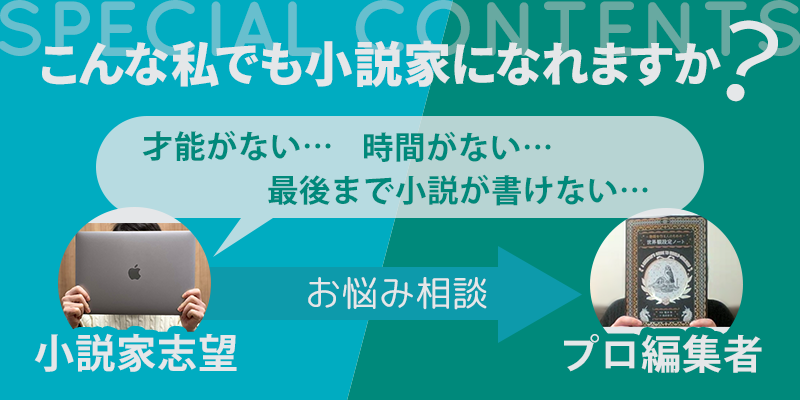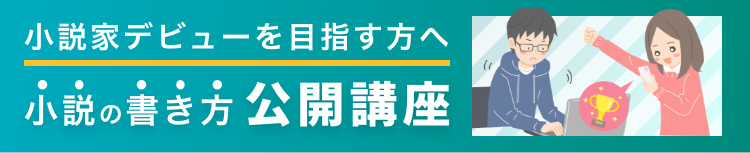

人物描写がうまくなるコツを知ってキャラクターを魅力的にしよう
エンタメ小説において魅力的なキャラクターを登場させることは不可欠です。個性的で愛されるキャラクターを作るためには、その人物像を上手に描写して、読者に提示しなければなりません。
この記事では、魅力的なキャラクター作りのために覚えておきたい人物描写の基本から応用まで、総合的にご紹介します。
目次
魅力的なキャラクターが生まれる人物描写のコツとは

物語は、主に登場人物の具体的な動作を表す描写で構成されます。しかしささやかな「仕草」や「雰囲気」「セリフ」も、より細かく人物を表現するために重要な部分です。キャラクターの仕草や雰囲気、セリフの描写は、登場人物の内面に起こる機微を表す方法としてとても適しています。
また、無意識に行う「癖」や深層心理を表す「仕草」などを描写することで、登場人物の人となりや感情の動きがわかりやすくなります。生き生きとした人間味を持たせて、魅力的なキャラクターを作っていきましょう。
「仕草」で心情や個性を表現するテクニック

セリフのないシーンでも、キャラクターの心情や個性を表現できるのが「仕草の描写」です。
- 立ち上がる、手を振る(動作)
- 髪に手をやる、腕を組む(仕草)
人がなんらかの意図をもって行う「動作」と違い、「仕草」は何気なくする、ささやかな所作を指します。視線を泳がせたり目を伏せたり、瞬きをするような目元の動きなども仕草です。
- 椅子に座っている
- 椅子に座って、貧乏ゆすりをしている
- 脚を投げ出して、椅子に座っている
ただ「椅子に座っている」という描写だけでは、その登場人物がどのような人柄なのかまではわかりません。しかしその人が「貧乏ゆすり」をしていれば、怒っている、イライラしている、などのイメージに。
「脚を投げ出して」座っていれば、奔放・大胆な人なのかなという印象を受けます。
このように細かい仕草の描写を入れると、さりげなくキャラクターの心情や個性を示せるのです。また、仕草の描写で、心情表現の幅も広がります。
- 「照れる」→鼻の下をこする、頭の後ろをかく、両手で顔を隠すなど
- 「驚く」→目を見開く、ぽかんと口を開けるなど
「照れる」や「驚く」という言葉を使わなくても、仕草だけで登場人物の心情が表せ、読者もイメージしやすくなります。人の内面を表現するのに苦手意識のある方は、仕草の描写を練習しましょう。
キャラクターの癖を描いて印象付ける(仕草のコツ1)
登場人物のその時の心情、内面を「仕草」で表せるなら、その人物が元々持っているキャラクター性はどのように表現したらいいのでしょうか。
人間は誰しも「癖」を持っています。「癖」は自分でも気づかないうちについついやっているものです。
- 爪を噛む、髪を触る、舌打ちする
癖によって登場人物の性格を表現するには、さまざまなシーンで何度か同じ仕草を描写するのがポイントです。
たとえば「舌打ち」をする描写が1回だけなら、怒っているのだな、うまくいかなかったのかな、と想像します。しかし他のシーンにも出すことで、「普段から気の短い人」というキャラクター性が印象付けられるのです。
その場の感情によって出てくる「仕草」と無意識でやってしまう「癖」では、読者にあたえる印象が変化します。
作中で描写する場合は、「癖から受ける印象と性格が一致しているか」を意識してどんな癖にするかを設定しましょう。
仕草に表れる深層心理とは? (仕草のコツ2)
仕草には、隠れた本性や本音が表れることもあります。ふとした仕草で、その人の深層心理がわかるという話を聞いたことがあるのではないでしょうか。
- 体の前で腕を組む
強い警戒心を抱いている。拒否や拒絶、自己防衛を示す - 小指を立てる
周囲から注目されるのが好き。女性らしさを強調している - 顎をさする
プライドが高く、相手を下に見ている。ナルシストや自信家に多い - 唇を舐める
ストレスや不安、緊張を感じている
このほかにも仕草には、さまざまな深層心理が隠されているようです。
調べてみるとおもしろいものですし、登場人物にある仕草をさせて、伏線的な意味を持たせるのも一手です。でも描写の度に1つひとつ調べていたのでは時間が足りなくなります。「ここぞ!」という場面を決めて使うのがいいでしょう。
「雰囲気」で人物像を表現するテクニック

キャラクターがもっている雰囲気の描写は、その人物像を表現するのに大きな効果を発揮します。雰囲気とはその人が身にまとっているイメージのことです。
- 透けるような白い肌の、奥ゆかしい雰囲気の女性だった
- 透けるような白い肌の、艶やかな雰囲気の女性だった
- 透けるような白い肌の、凛とした雰囲気の女性だった
外見や内面以外にも、「雰囲気」を描写することによってキャラクターのイメージを伝える方法があります。どれも「透けるような白い肌の女性」であることに変わりはないのですが、雰囲気を付け足すだけで違う人物を想像したのではないでしょうか。
そのキャラクターがはじめて登場するシーンでも、雰囲気の描写があることで、読者はその人物を想像しやすくなります。
「セリフ」で境遇や性格、感情の動きを演出するテクニック

キャラクターの人物像は誰かと会話をすることで表出しやすくなります。
1人でなんらかの行動をさせるよりも、会話の相手がいることで、「心の動き」を言葉で表現できるようになるのです。
生まれ持った性格、境遇、考え方などが違う複数のキャラクターを想像してみましょう。その人物それぞれが「酔っ払いにからまれた」場合、どのような言葉を返すでしょうか。
相手に返す言葉の内容や口調、そこからにじみ出る感情もキャラクターによってさまざまです。キャラクターによって対処方法が異なるようなシチュエーションを用意することで、人間性の違いがわかりやすくなります。
キャラクターの性格を書き分けたいときは同じシチュエーションならどのようなセリフが出るかを考え、会話の生まれる状況を取り入れましょう。
キャラクターの口調で与える印象が変わる(セリフのコツ1)
感情が動き会話が生まれることで、キャラクターの人間性を表現しやすくなります。さらにその人物の「言葉づかい・口調」によっても印象は変わるものです。
- お前に付き合ってほしい場所があんだよ。危険な目には合わせねぇ。
- あなたに付き合ってほしい場所があるんです。危険はありません。
- 君に付き合ってほしい場所があるんだ。危険なところではないよ。
どれも「一緒に来てほしい場所がある」というセリフです。話している内容は同じですが、頭に浮かぶキャラクターはそれぞれ違うものではないでしょうか。
1は「お前」という二人称、ないことを「ねぇ」という部分から、荒っぽさを感じさせます。
2は目上の人を相手にするときのような、丁寧さを感じる口調です。3つのなかではもっともやわらかい印象があります。
3は丁寧でやわらかい口調ではあるものの、どこか威圧的な印象を受けます。
これは「君」という二人称によるもの。「君」は自分と同等かそれ以下の立場にある相手に対して使う呼び方だからです。
キャラクターのセリフは、その口調によっても読者に与える印象が変わります。登場人物の個性を出すための大切な要素なので、キャラクターの性格に合っているかどうかを意識して決めましょう。
一人称で印象に変化をつける(セリフのコツ2)
キャラクターに個性を持たせるためには、一人称の使い方に変化をつけることも重要です。自分のことを「僕」と呼ぶのと「俺」という呼び方をするのでは、それだけで受ける印象が違います。
- 「俺」は男性的な一人称
- 「私」は女性的、丁寧な一人称
- 「僕」は男性的でもやわらかい印象の一人称
上記が一般的な一人称とそのイメージです。一人称には、さらにさまざまなバリエーションがあります。たとえば同じ「僕」でも、カタカナで「ボク」、ひらがなで「ぼく」ではそれぞれに印象が違ってくるのです。
- 「僕」は幅広い年齢で使える一人称
- 「ボク」はせいぜい10代まで、あるいは女の子が使うケースもある
- 「ぼく」は年齢一桁の子どもに使わせるのが自然
このようにキャラクターの性質の違いは一人称で表現できます。とはいえ、必ずそうしなければならないというわけではありません。
たとえば20代のキャラクターに「ボク」を使わせることで、内面の幼さを演出できます。またボーイッシュな女の子に「オレ」を使わせて、その個性を印象付けるパターンも定番。
ヒロインの前では「俺」でも、職場では「私」と使い分ければ、キャラクターの「社会性」を演出する方法として効果的です。
キャラクターの使う一人称が違うだけでも、その人物への想像は膨らみます。どんなキャラクターがどの一人称を使いそうなのか、じっくり考えてみましょう。
特徴的な口調でキャラクターを立てる(セリフのコツ3)
一人称だけでなく、口調を特徴的にすることでキャラクターを印象付ける方法もあります。
- 男性的な言葉「~だぜ」
- 女性的な言葉を使う「~わよ」
- 敬語を使う
- 方言を使う
なにも、「~だにゃ」「ざます」のような特殊な語尾を使う必要はありません。上記のように自然な方法でキャラクターの口調に特徴を持たせるのもいいでしょう。意識して口調に変化をつけると、どんな人物なのか想像しやすくなります。会話文でも誰のセリフかがわかりやすいのでオススメです。
服装や容姿の描写が難しい? 人物の外見を表現するコツ

人物描写をするとき、みなさんはキャラクターのビジュアルまで細かく設定していますか?
よく見かけるのが、登場人物の服装や体つき、顔の造詣に髪型などの情報が全くないケースです。実在の人間は人それぞれに容姿が違って当然。人物描写をするときは、「個性」までしっかりと表現したいものです。
顔つきを描写する
人物の顔つきを表現するときに「美人」や「美形」だけで済ませてしまう人も多くいますが、実際にはさまざまなタイプがあるはずです。
- 二重で目がぱっちりして、鼻が高いはっきりとした顔立ち
- 色白で切れ長の瞳のシャープな顔立ち
一口に美人といっても、思い浮かべる顔立ちは人それぞれ。作者の頭の中にあるビジュアルを正確に伝えるためには、細かい造詣の部分までしっかりと言葉にする必要があります。
実在する人物の顔立ちをよく観察し、特徴を文章にしてみるのもいい練習です。
体つきを描写する
登場人物の顔立ちはイメージできていても、体つきまではよく考えていなかった、というパターンも多いものです。身長や体重、筋肉量などの情報は、スポーツやバトルなどの動きのあるシーンにリアリティーを出すために重要な要素。しっかり設定しておきましょう。
細い腕で大きな斧を振り回す少女のキャラクターや、筋骨隆々の大男だけどとても優しい性格のキャラクターなど、登場人物の魅力を引き出すにも、体つきの描写は必要です。
スタイルの良さを表したいときも、具体的な「足の長さ」「腰の細さ」などを細かく書いていきましょう。どんな風に魅力的なのかを文章にして、読者にイメージしてもらうのが大切です。
髪型を描写する
髪型の表現は登場人物が女性の場合は、自然に書けている人が多い傾向です。ショート、ミディアム、ロングといった大まかなくくりから、ストレートなのかウエーブがかかっているのか、という違いも。
また髪の結びかただけでも、ポニーテールやツインテール、おさげなどヘアスタイルに詳しくない人にも伝わる、有名な表現がたくさんあるからです。
一方、登場人物が男性となると、一転、髪型の描写の難易度が上がります。それは男性のほとんどが「ショートヘア」だから。坊主頭やロングヘアという特殊なスタイルはそれだけで個性になり得ますが、ふつうのショートヘアの書き分けは難しいかもしれません。
うまく書くコツは「くわしく描写すること」です。ショートヘアという小さなくくりのなかにも、襟足の長さや、前髪の形、分け目をどこにするかでも印象は変わります。またくせ毛なのか、直毛なのか、毛先を遊ばせている、逆立つようにスタイリングしている、などの違いも人物の個性につながります。
服装を描写する
登場人物が身にまとっている服装でも、キャラクターの個性を表現できます。しかし小説を書いている人の中には、服装の描写に苦手意識を持っている人が大勢いるようです。
ファッションに対して詳しくないという苦手意識からついつい身近な、パーカー、Tシャツ、ジーンズ、という表現で済ませてしまうのは非常にもったいないこと。特にファンタジーの世界を描く場合は、現代の日本の常識にとらわれず、さまざまな色使いや形状の服装を着せられるはずです。それが登場人物の個性や魅力にもつながります。
キャラクターの魅力を引き出す服装を表現する(着せる)ためには、自分の好きな小説やアニメのキャラクターをイメージするのが近道です。その形状や色合いを調べて参考にしていましょう。
ただし馴染みのないファッション用語を無理に使う必要はありません。かえって読者に伝わりにくくなる可能性があるからです。
たとえば腰から裾までのシルエットがまっすぐな「ペンシルスカート」という種類のスカートがあります。この場合、ペンシルスカートと書くより「腰から裾までのシルエットがまっすぐな、細身のスカート」と書いた方が映像として浮かびやすくなります。
装飾品を描写する
忘れてはいけないのがアクセサリーの類です。特に女性キャラクターの外見を描くときのアクセサリーの役割は大きいもの。地味なタンクトップにジーンズという出で立ちでも、大きなゴールドのループピアスを着けているのと、羽の付いた髪飾りと自然石のネックレスを着けているのとでは、大きく印象が変わるのではないでしょうか。また、まったく装飾品を着けていない、という描写でも人物の個性を表せるのです。
男性キャラクターの場合も、装飾品でイメージが変わります。どんな眼鏡をかけている、どんな腕時計をしている……ファンタジーなどでは、武器も装飾品と同様の役割をするケースも。短剣なのか、サブマシンガンなのか、それもどのくらいの大きさでどんな飾りがあって……と細かく設定していきましょう。
人物の「色」を描写する
登場人物の服装の色や、髪の色、瞳の色などについてもしっかり設定しておくのがオススメです。それはエンタメ小説やライトノベルでは、イラストが挿入されたり表紙になったりというケースが多く見られるためです。イラストレーターは、作者が設定した外見をもとに作画をします。
ここで何も考えずに色を決めてしまうのはNGです。日本が舞台の小説ではつい全員黒髪、黒い瞳となってしまいがちですが、こうなると華がありません。パッと見でキャラクターを判別できないのも問題です。イラストの入らない小説の場合も、同じような表現の連続になってしまうため、読者はイメージしづらくなります。
なにもアニメのようにピンクや黄色の髪色にすればいいというわけでもなく、ここは小説家の表現力が試される部分。ヒントは、同じ黒髪でも艶のある濡れ羽色と、赤みがかった黒髪では印象が違います。このような些細な違いを描写できると、人物描写の表現の幅は大きく広がります。
人物の外見を描写するときの注意点
登場人物の外見について、表現の方法をお伝えしてきましたが、実際に文章にするには、その見せ方に工夫が必要になります。注意点としては「一気にすべてを描写しないこと」
キャラクターが初登場するシーンではある程度見た目についての説明があるべきです。しかし服装の細かい装飾などの説明まではじめてしまうと、読者にとっては情報が多すぎて飽きてしまう原因に。大切なのは、登場人物の「感情の動き」なので、そちらを優先するのが鉄則です。
細かい描写はストーリーを進めていく中で自然にみせていくようにしましょう。初登場のときに示されたざっくりとしたイメージが、ストーリーを読み進めるうちにどんどん細かい情報が追加され、徐々にイメージがはっきりしていくのが理想的です。
登場人物の属性・立ち位置の書き分け方
人物がどんな属性か、どんな立ち位置にいるかによっても求められる描写のやり方は変わってきます。ここでは物語における登場人物の立場ごとに書き方のポイントをおさらいしていきます。
主人公のパターン
主人公をどのように描写するかで、物語の方向性が決まります。読者が誰に感情移入し、誰の目線で物語を追ってくのか、その中心となるのが主人公です。またどんな人物にするのかが他のキャラクターにも影響するのでしっかりとその「役割」を考える必要があります。
※主人公の書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください
キャラクター設定と作り方【主人公編】
ヒロインのパターン
魅力的なヒロインは物語の華です。代表的な人物像としては2つ。「塔の中のお姫様タイプ」と「バトルヒロインタイプ」です。前者は文字通り、何らかの事情で自らは行動できず、主人公の助けを待つヒロイン像。後者は主人公と共に戦う勇敢なヒロインです。
どちらもその役割は「主人公の背中を押し、物語を進めていく」こと。読者が思わず夢中になってしまうような魅力的なヒロインを描きましょう。
※ヒロインの書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください
キャラクター設定と作り方【ヒロイン編】
ライバル関係のパターン
主人公やヒロインと同等に重要なのが「敵対する関係の人物」です。最強の敵や格上のライバルは、主人公の成長を描くために欠かせない存在。読者にとって憎むべき相手でありながら、アメコミヒーローものに登場する、スーパーヴィランのように惹きつけられる魅力を持った人物描写ができると物語は格段に面白いものになるでしょう。
※ライバル関係の書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください
キャラクター設定と作り方【ライバル・黒幕・敵編】
脇役のパターン
主人公の引き立て役でありながら、物語の歯車として欠かせない存在なのが「脇役」です。物語を動かす大切な役割がありながらも前に出すぎてもいけない、もっともポジション取りの難しい登場人物だともいえます。
主役級キャラクター達とは違った考え方や信念を持たせることで、彼らの個性を引き立てるパターンが定番です。
※脇役キャラクターの書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください
キャラクター設定と作り方【脇役キャラクター編】
小説の登場人物を魅力的にする方法総まとめ

よりリアルな人物像を追求するためには、そのキャラクターを深く知りたいという気持ちが大切です。ここでは登場人物のキャラクター性を掘り下げ、まるで実在する人物のように描く方法をまとめています。
登場人物のキャラクター性を掘り下げる方法
魅力的な人物描写をするためには、キャラクターの人物像を細部まで考えることが大切です。その人物がどんな人生を歩んでいたのか、何を好むのか、そのキャラクター性を掘り下げることで、人物描写に深みが出てきます。
キャラクターへの質問を作り、その人物になったつもりで回答していく方法などを使って、よりリアルな人物像を作り上げましょう。
※キャラ作りの具体的な方法について詳しくは以下の記事をご覧ください
キャラ作りに役立つ3つの要素とキャラクターへの質問集
キャラクターは名前でもイメージが変わる
名前の付けられたキャラクターが登場すると、読者はその人物が物語の中で重要な存在だと認識します。読者は名前にある漢字が持つ意味や音の響きから、その人物像をイメージすることも多いので、適当に付けた名前ではいけません。その人物の親になったつもりで、素敵な名前を付けてあげましょう。
※キャラクターの名付けに悩んだら以下の記事を参照してください
キャラクターの名前の付け方
読者の「共感」と「憧れ」を引き出し感情移入を誘う方法
多くの読者が小説を読む目的は、「自分とは縁のない出来事を疑似体験するため」です。よりリアルな体験を提供するには、キャラクターの人物描写にこだわらなければなりません。自分には関係のない世界を、どうすれば「自分事」として感情を揺さぶれるのか。
そのヒントは「共感」と「憧れ」にあります。
読者の心をつかむためには登場人物に対する「憧れ」が必要です。しかし完ぺきな存在というだけでは「共感」はしにくいもの。
読者の「こうなりたいな」と「その気持ちわかる!」を同時に引き出してこそ、愛される人物描写ができるのです。
※「共感」と「憧れ」を引き出す具体的なテクニックについては以下の記事をご覧ください
キャラクターがもっと魅力的になる書き方
人物描写の応用編|情景描写で心情を表す
エンタメ小説ではわかりやすさが大きなポイントになります。誰もが頭の中でイメージできるように簡単な表現を選ぶ必要がありますが、それだけでは物足りないことも。情景描写を上手に使えば、より印象的に登場人物の気持ちを表現できます。
登場人物が悲しくて泣きたい気持ちならば、そぼ降る雨の描写を使う。怒りが込みあげている場面では沸騰する鍋の描写をする。このように「悲しい」「腹が立つ」という言葉を使わずに、人物の気持ちを描写すると、ストレートな描写よりも深く伝わります。
※情景描写の書き方について詳しくは以下の記事をご覧ください
風景・情景描写の書き方
人物描写が魅力的なら物語のおもしろさもワンランクUP!
小説の人物描写では、キャラクターの外見や具体的な行動だけでなく、その人物像や感情などを、どれだけ読者にイメージさせられるかが重要になってきます。
項目ごとに意識して人物描写を練習することで、あなたの小説の登場人物はより魅力的で生き生きしたキャラクターになることでしょう。人物描写のコツを意識して、キャラクターに魂を吹き込みましょう!
【関連記事】
小説表現のワザと書き方のコツ
この記事は小説家デビューを目指す方を対象に作られた小説の書き方公開講座です。
幅広いテーマで書かれた数多くの記事を無料でお読みいただけます。
榎本メソッド小説講座 -Online- のご案内
お読みいただいているページは、現場で活躍する小説家・編集者・専門学校講師が講師を務める、小説家デビューを目的としたオンライン講座「榎本メソッド小説講座 -Online-」の公開講座です。小説家デビューに向けてより深く体系的に学習したい、現役プロの講評を受けてみたいといった方は、是非本編の受講をご検討ください。
監修|榎本 秋
1977年東京生。2000年より、IT・歴史系ライターの仕事を始め、専門学校講師・書店でのWEBサイト企画や販売促進に関わったあと、ライトノベル再発見ブームにライター、著者として関わる。2007年に榎本事務所の設立に関与し、以降はプロデューサー、スーパーバイザーとして関わる。専門学校などでの講義経験を元に制作した小説創作指南本は日本一の刊行数を誇っており、自身も本名名義で時代小説を執筆している。
同じカテゴリでよく読まれている公開講座
-
SF小説の書き方
SF小説の魅力は「現実離れした世界観」。そこはファンタジー小説と共通するところですが、SF小説というジャンルではより現実的な描写が必要となります。 SF小説には細かい分類がたくさんあります。ありすぎるため、自分の書きたい […]
-
キャラクターの名前の付け方|ポイントとストック方法
「キャラクターの名前がなかなか決まらず、締切に間に合わせるため適当な名前になってしまった。」 「登場人物が多くなりすぎてキャラクター名が似てしまったり、雑になったりしている。」 このような名付けの苦労は、小説家としてデビ […]
-
児童文学の書き方
小説家を志す方のなかには、児童文学作家になりたい、児童文学を書いてみたい、という人も多いのではないでしょうか。もし「簡単そうだから……」という理由であるのなら、それは間違いです。 児童文学は、子どもに好かれるような面白い […]
公開講座 - 目次
カテゴリから探す
ジャンルから探す
人気の公開講座